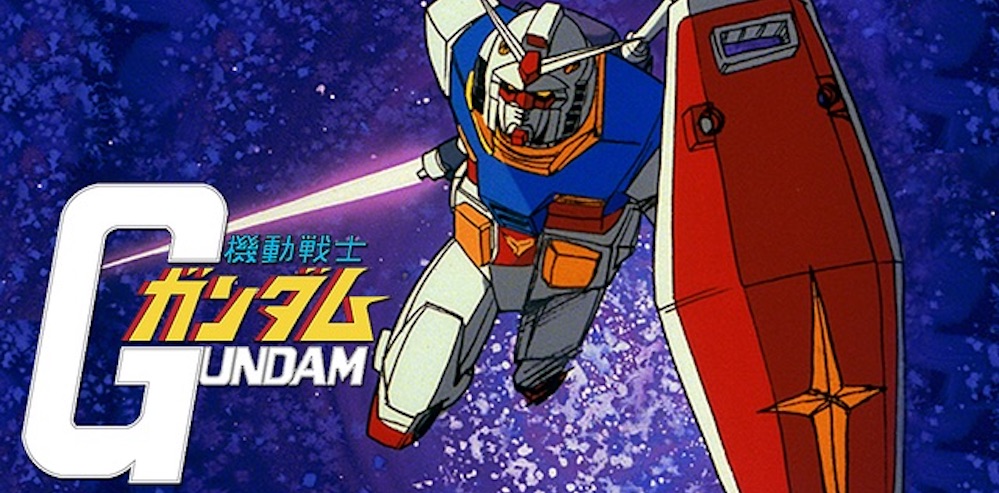■第13話「再会、母よ…」
脚本/星山博之 演出/藤原良二 絵コンテ/ 作画監督/安彦良和
あらすじ
 ホワイトベースは、海岸でしばしの小休止を取っていた。故郷が近かったため、アムロは許可を得て母に会いに行く。しかし、母の住む家では連邦兵がたむろしており、ここには誰もいなかったとアムロに告げる。近所のおばさんから話を聞いたアムロは難民キャンプでボランティアをする母と再会する。一方ジオン軍は、偵察機が警戒を続けていた。その動きを察知したブライトはリュウをコアファイターで出撃させる。
ホワイトベースは、海岸でしばしの小休止を取っていた。故郷が近かったため、アムロは許可を得て母に会いに行く。しかし、母の住む家では連邦兵がたむろしており、ここには誰もいなかったとアムロに告げる。近所のおばさんから話を聞いたアムロは難民キャンプでボランティアをする母と再会する。一方ジオン軍は、偵察機が警戒を続けていた。その動きを察知したブライトはリュウをコアファイターで出撃させる。
コメント
13話は第2クールの幕開けである。前話で「巨大な敵」であるジオン公国が全容をあらわし、主人公らホワイトベースの目の前には、新たにランバ・ラル部隊が敵として立ちはだかった。これから、「ザクとは違う」新型との熾烈な戦いが・・・と期待を持たせるところだが、これから2、3話はそこからそれた、足踏みのような話が続く。しかし「ガンダム」のエッセンスが凝縮されたエピソードとして、この辺りのストーリーを思い出す人は多いだろう。シャアという強烈なキャラクターが「左遷」という形で表舞台から去った中、いよいよ物語の核はアムロとホワイトベースの面々の内側へと降りてくる。
太平洋上で遭遇したランバ・ラル部隊との戦いを何とか切り抜けたホワイトベースは、とある海岸で小休止していた。この場所がどこかは、ナゾである。ガンダムブーム全盛期の1981年に刊行された徳間書店の「ロマンアルバム・エキストラ35 機動戦士ガンダム」によれば、この場所は「日本」ということにされている。これは鳥取だ、という話もあったが、恐らく背景に描かれた砂丘のような風景から、そういうことになったのだろう。しかし劇場版では12話と13話の順序が入れ替わったため、この場所はカナダのプリンスルパートということにされていた。
この脚本を書いた星山博之氏の著作「星山博之のアニメシナリオ教室」には、本作の決定稿(ライターが書き上げ、監督、プロデューサーがゴーサインを出して印刷されたもの)と録音台本(絵コンテ、演出のカット構成作業によって作り替えられたアフレコ前の台本)の両方が収録されている。これによれば、決定稿では冒頭の海岸は「サンイン」と書かれており、もともとは日本の山陰地方を想定して書かれていたことがわかる。


日本の山陰地方の海岸に停泊するホワイトベース。鳥取県の浦富海岸あたりの風景にとても似ている。小休止で日光浴を楽しむミライとセイラ。アムロが母を訪ねて行ったと聞いたカイは…
故郷の近くにホワイトベースが停泊した。そこで許可をもらってアムロが母親に会いに行く、という話である。しかし「再会、母よ」というタイトルコール(鈴置洋孝が務めている)は重々しい。再会が、果たして幸せな時間をもたらすものなのかどうか、不安を憶える幕開けである。
海岸でミライやセイラが日光浴を楽しむなか、アムロはコアファイターで故郷を目指していた。カイはミライからそれを聞いて「ヘッ、裏切られたな。奴もエリート族かよ」と吐き捨てるように言う。地球に家がある、それだけで特権だというのである。先にランバ・ラル部隊は一枚岩だ、と書いたが、彼らは地球連邦という地球とスペースコロニーの両方にまたがる巨大国家に属しているだけに、境遇も立場も千差万別で、ただ地球連邦だというだけでは一つになれない、大きいがゆえの脆さがあると感じさせられる。


母の暮らす故郷へ向かうアムロの表情は明るかったが…。母の住む家を探しあてて飛び込んでいくアムロ。背景に見えるのは鳥取砂丘か。


しかしそこには呑んだくれた連邦兵士らがおり、この家には誰もいなかったと聞いたアムロはショックを受ける。近所のおばさんから事情を聞き、母の居所を知ったアムロは…
アムロは母の住む家を探しあてて飛び込んでいくが、そこでは連邦軍の兵士が無断で入り込み、音楽を鳴らして飲んだくれていた。その中の一人が言うには、ここは空き家になっていたのだ、という。母は死んでしまったのだろうか・・・。不安に駆られたアムロは、屋台でリンゴを売る女性に金をきちんと払おうとしない連邦軍兵士に腹を立て、飛びかかっていくのだった。
その屋台の女性がアムロを思い出したことで、母の居所がわかる。難民キャンプでボランティアをしているというのだ。ちなみに彼らのいるこの地域は、今はジオンの勢力下にあるようだ。屋台の女性によれば「生き残った兵隊さんは本部から見捨てられちゃってね。仲間が助けに来ないもんだからあんな風になっちまって。」ということらしい。どこまでも頼りにならない連邦軍であるが、この話は、旧日本軍の兵士たちの哀れな末路を思い起こさせられる。「やだねえ、戦争って」と女性は続ける。兵士たちを責めているのではない。そのような状況をもたらした戦争を恨んでいるのだ。
難民キャンプには、老人と親を失った子どもたちがいた。老人たちは、アムロのコアファイターが敵に見つけられては困る、と警戒している。北米大陸のイセリナ・エッシェンバッハ父子とは違い、ここの人々はジオンに対する抵抗感がまだまだ強いようである。まだ小競り合いが続いているような状況があるということかもしれない。そんな中、アムロは母と再会を果たす。幼少の頃、宇宙の暮らしになじめないという理由で母は父とアムロと離れて地球に残る選択をした。そんな母との、久方ぶりの再会である。抱き合う母子を見て「いいなー」とつぶやく子どもたちの姿が印象に残る。


母がボランティアをしていた難民キャンプを訪れたアムロは、母との再会を果たして抱き合う。


その様子をうらやましそうに見る戦災孤児たち。母はサイド7の空襲でアムロの父が行方不明になったことを聞いて表情を曇らせる。
しかし、そこへジオン軍の兵士が見回りにやってくる。敵の戦闘機らしきものが着陸したという報告があったというのだ。折しもホワイトベースでは、敵の哨戒機を発見し、リュウのコアファイターと交戦しているところであった。母は病人を装ってアムロを庇う。しかしそのとき、ホワイトベースからアムロを呼び出す通信音が鳴った。ベッドに寝ているのは誰か、と問いつめるジオン兵。追いつめられたアムロは、やおら起き上がるとジオン兵に向けて発砲する。


ジオン兵が巡回に来た時に通信音が鳴り、窮地に陥ったアムロは、ジオン兵に向けて発砲した。驚く母。
銃弾が当たって負傷した兵士1人を置いて、他のジオン兵は逃走していった。しかしアムロは戸口に立ち、玉切れになった拳銃をいつまでも撃ち続ける。これまでジオンのザクに銃口を向けてきたアムロだったが、生身の人間に対して生身で対峙し、発砲したのはこれが初めてのことだった。アムロとしては、決死の覚悟で兵士として最善と思える策をなした、ということだったのだろう。しかし、母親の受け止め方はまったく異なっていた。
「あ、あの人達だって子供もあるだろうに、それを鉄砲向けて撃つなんて…すさんだねえ」
自分の息子が、目の前で敵に向かって発砲する。もしかしたら、人の命を奪ってきたかもしれない。そんな状況に平静でいられる母親はいないだろう。こんなことがなければ、息子と母親は再会を果たし、そして息子は軍隊を離れて母のもとに残ったかもしれない。しかし、だからといってアムロがガンダムに乗って、敵を倒してきた事実は変わらない。


虫も殺せなかった子が…と、アムロの変貌を嘆く母。一方アムロはカイの誘いで、ろくに訓練もしていないガンダムの空中換装にトライする。



やけくそ気味にジオンの前線基地を攻撃するアムロ。それを見て、単なる消耗戦だとキレるブライト。しかし母親の前では「めざましい活躍でした」とアムロをおだてた。
私の母は戦中に生まれた世代だが、戦争が終わったあと、近所には戦地から帰ってきた人たちがたくさんいたという。中には親と知り合いの近所のおじさん、おにいさんもたくさいたことだろう。しかし彼らは決して、戦争の話をしなかったと言っていた。戦争で被災する者と、戦地に出て敵を倒す者。そこには、ともに共感することを妨げるような「壁」があったのかもしれない。それを感じたからこそ、戦地に行った者は戦地のことを語れなかったのだ。本作は、その「壁」をこそ描いた、といってもいいだろう。
それでも、こんなことが目の前で起きなければ、「壁」の内外でお互いに安住していられたかもしれない。しかし状況はそれを許さなかった。11話「イセリナ、恋のあと」で描かれた「わかりあえない2人」の相互不理解と、その究極である戦争というテーマがここにある。だからこそ、「再会、母よ…」は「ガンダム」を代表するエピソードとなっているのだろう。
この一言! 「嫌とかじゃないんだ。あそこには仲間がいるんだ」
 「人様に鉄砲を向けるなんて」という母に、アムロは言葉を振り絞るようにして言う。
「人様に鉄砲を向けるなんて」という母に、アムロは言葉を振り絞るようにして言う。
「母さん、母さんは、僕を愛していないの?」
やや唐突に思えるこの言葉だが、恐らくそれは、今ここで出てくるまでに長い年月を経た言葉だったかもしれない。
母の暮らす故郷の家で、アムロが古びた木の人形を手に、母と別れた日のことを回想する場面がある。父はサイドの建設をアムロにも見せたい、とスペースコロニーへの移住を決意する。しかし母は「宇宙の暮らしには馴染めない」と地球に残ることを決めた。そのために、アムロは母と離ればなれに育つことになったのだ。
 そんな母親が、敵に発砲したアムロに「そんな子に育てた覚えはない」と言い放つのには理不尽さを感じるだけに、アムロが反発するのも無理はない。それ以上に、空き家になった故郷の家で、アムロが思い出したのが、母と過ごした楽しい日々ではなく、別れの日のことだったことは大きな意味があっただろう。「なぜ・・・」。なぜ、母さんは一緒に来てくれなかったのだろう。心の中には、そんな思いがわだかまっていたはずだ。図らずも、この再会の時に起こった出来事によって、アムロはわだかまる思いにあてまはる言葉を見つけた。それが「母さんは、僕を愛していないの?」ということだったのではないだろうか。
そんな母親が、敵に発砲したアムロに「そんな子に育てた覚えはない」と言い放つのには理不尽さを感じるだけに、アムロが反発するのも無理はない。それ以上に、空き家になった故郷の家で、アムロが思い出したのが、母と過ごした楽しい日々ではなく、別れの日のことだったことは大きな意味があっただろう。「なぜ・・・」。なぜ、母さんは一緒に来てくれなかったのだろう。心の中には、そんな思いがわだかまっていたはずだ。図らずも、この再会の時に起こった出来事によって、アムロはわだかまる思いにあてまはる言葉を見つけた。それが「母さんは、僕を愛していないの?」ということだったのではないだろうか。
アムロは自暴自棄気味に、叩く必要のないジオンの前線基地を攻撃する。合流したホワイトベースのブリッジで、そんなアムロの戦いを「単なる消耗戦だ」と切り捨てるブライトだが、まだ正規の軍人でないアムロには、他の避難民がそうしたように、母の元に残るという選択肢も与えられていたようだ。だからこそ母は知人の車でホワイトベースの停泊地までやって来ていた。「嫌なのかい?」という問いかけは、そのことを言っているものと思われる。
 「嫌とかじゃないんだ。あそこには仲間がいるんだ」
「嫌とかじゃないんだ。あそこには仲間がいるんだ」
残るように母が勧めている、ということは、「人様に鉄砲を向けるなんて」とアムロをなじったりしたものの、戦争の中でやむを得ない状況とそれを受け止めて、それでも息子を受け入れ、これ以上戦いに関わることのないようにしてやろうという親心があったに違いない。しかし、アムロは言う。あそこには仲間がいる、と。仲間といっても、「なんだ、アムロもエリートなのか」と言い捨てるような、いまだ絆もなにもない烏合の衆である。あそこには仲間がいるんだ。なんという虚しい言葉だろうか! それでも、彼にとっては仲間である。彼らのために命がけで戦ってきた、という事実がある。それが、アムロを辛うじて支えているプライドなのだ。
「映像の設計図」としての脚本、そこから立ち上がる「富野節」の妙
この13話「再会、母よ…」は、本作の中でも屈指の傑作エピソードといわれている。それまでは、どちらかというと亡き父母の思いを胸に戦う、といった立場で描かれることの多かったアニメの主人公だが、このエピソードのテーマはそれとは真逆の「生きている母との訣別」だからだ。そこには、イセリナ父娘との間でも描かれたような「わかりあえない二人」の「相互不理解」、もっと端的にいうならは、母と子との間の「断絶」が描かれている。
下記リンクは、ブックレビューで紹介した「星山博之のアニメシナリオ教室」。先述したように、この本では、脚本家による決定稿と、アフレコ台本が掲載されており、脚本家の書いたシナリオが、映像を作るという過程を経てどう変わるのかを比較して見ることができる。
ブックレビュー:名作を生み出す〝映像の設計者〟の仕事とは〜星山博之著『星山博之のアニメシナリオ教室』
脚本家の星山博之氏は、シナリオライターとは「映像の設計図を作る仕事」だと著書の中で述べている。「母との訣別」をテーマに据え、ホワイトベースの停泊地から、再会に胸をふくらませながら故郷の母を訪ねたアムロが、敵兵との遭遇と銃撃をきっかけに、その関係性が離れていた時間と、そして何より戦争によって切れてしまっていることに気づき、母との別れを決意するというストーリーの全体像を作り上げた。
そのシナリオでは、アムロや母の会話など、実際にアニメになった場面にくらべ心情を言葉で語らせているところが多いように思えたが、それはシナリオがあくまで「設計図」だからであって、ここから場面を絵として起こし、キャラクターたちを動かしていくという過程を経て出来上がったアフレコ台本では、そのセリフは極限まで削ぎ落とされ、セリフによって説明されていたことが、キャラクターの表情や仕草など、絵の「演技」によって表現されているのだとわかった。
そうして削ぎ落とされたセリフの中に、刺さるような一言で、状況や心情を見るものに悟らせる、そんな演出の妙がある。このレビューの「この一言!」で掘り下げたアムロの「母さんは、僕を愛していないの?」というセリフ、そしてラストの母との別れの場面、「嫌とかじゃないんだ、あそこには仲間がいるんだ」から始まる、ブライトを交えた母とのすれ違ったままの会話、これらはシナリオが映像化されていく部分で、セリフがかなり変えられている。逆にいえば、これらのセリフは、映像化の過程を通して生まれ出てきたものなのだ。それが演出の妙であり、「富野節」ともいわれる、監督・富野由悠季氏の表現なのだろう。
なぜ、日本なのか
最後に、この「再会、母よ…」の舞台設定がなぜ、日本になっているのか、ということに触れておきたい。
本作が制作された1970年代当時は、子どもをターゲットにした漫画やアニメ作品の主人公は日本人でなければならない、というある種の縛りがあった。そうでなければ、視聴者である子どもたちが、主人公に親しみを持てないから、ということがあったのだろう。そんな中、近未来を舞台にした本作では、主人公のアムロ・レイをはじめ、国籍や民族性を感じさせないネーミングがされていることも、斬新さを感じる点だった。しかし、設定資料には「アムロ・嶺」と記載されているように、主人公は日本人なんです、という弁明がスポンサーに対してできるようにされていたようだ。
そういうこともあり、アムロの故郷もそれとはなしに日本ということになり、ちょうどホワイトベースが太平洋を横断して北米から中国へ向かう途中ということで、アムロが故郷を訪ねて母と再会する、というエピソードが考えられたのだろう。
ただ、そうした都合だけで、このエピソードの舞台が日本になったというのではなく、日本が舞台だからこそ、母と再会したが、その母を切り捨て旅立つ、という少年の自立のストーリーを描こうと星山博之氏は考えたのではないだろうか。というのは当時から現在に至るまで、こと日本においては、母親と子の「母子癒着」、子の自立を阻む母親、というのが、成長した子の人間関係を蝕む要因になっているからである。母親が子を巣立たせようとしないなら、子が自ら母を切らなければならない、そう、子は母を捨ててもいい。一見重苦しく悲しい結末に思えるこのエピソードの中には、日本に生きる子どもたちへの、肯定的なメッセージがこめられているのだ。
<今回の戦場>
太平洋・島嶼地帯の沿岸部
<戦闘記録>
■地球連邦軍:ジオンの哨戒機を追跡、撃墜し前線基地を叩く。
■ジオン公国軍:哨戒機が発見され交戦、撃墜され前線基地も攻撃を受ける。